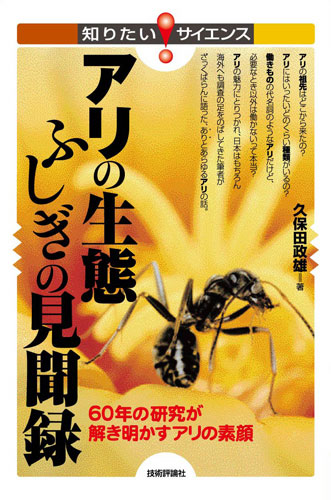アリとともに40年の雑感 −「あとがき」に代えて
TOP > アリとともに40年の雑感 −「あとがき」に代えて
毎回のように虫に刺されたり、血を吸われたり、時には咬まれたら命のない毒ヘビとのニアミスも再三ならずあった。マレー半島やボルネオあたりの森林には、やたらとトゲのある植物が多いところがあり、半日も歩き廻ってくると、体には数10本のトゲが刺さってしまう。全部は取りきれないで、いつもたいてい何本かのトゲを“みやげ”に、日本に帰ってくる始末であった。「自分の貯金をはたいて、伝染病や風土病の多い熱帯まで、何がおもしろくて出かけるのか?と、不思議がる人もある。それもこれも、ただ熱帯雨林地帯には、まだ世に知られていない、変わったアリがたくさんいるからである。
・・・・・・思えば、あの敗戦後の非常に困難な時代にアリの研究を思い立ち、ついには東南アジアのアリを、研究に役立つ程度にまで収集しようという考えは、どうやら身の程を知らない試みだったようだ。欧米の博物館や大学には、100年前後の歴史を誇る立派なアリのコレクションがあり、それらと張り会うには、とうてい私一代では無理である。最近では、採集した標本や文献も増えて、その整理さえも怪しくなってきた。
動物界全体を見渡すと、いろいろなグループで、独自の社会生活が発達してきたことがわかる。このような動物が、どうして社会生活を営むようになったのか、個々の個体がどのようなしくみで社会に結びつけられているのか ─ これは社会生物学のいちばん重要な命題だが、まだ納得のいく説明は得られていない。私たちは、人間自身をよく知ることが最も大切だ、と思うのだが、アリの研究成果が直接、人間社会の解明に役立つ、とは考えられない。むしろ、両者が意図的に結びつけられることを恐れている。
旧制中学で教鞭をとっていたある日、隣の県立中学生が、アリのことで私を突然訪ねて来た。このまだ童顔の少年とは、それ以来、ずっと親しくおつきあいをしているが、40年後の少年こそ、白梅学園短大の近藤正樹教授である。また、近藤教授の大学院時代に、一人の大学生が彼の仕事を手伝いに現れた。この生物学科に籍を置く学生は、われわれに接触するまで、アリには黒アリと赤アリがいる、という程度の知識しかなかった。この学生が、今は染色体進化の理論研究で知られる国立遺伝学研究所の今井弘民博士である。不思議な縁(えにし)を今さらながらに思わずにはいられない。
この両氏をはじめ、多くの友人、知人には何かと支援を受けてきた。海外の調査に当たっては、現地の大学、研究所のスタッフから、さまざまな温かい便宜を与えられた。いちいち名前は記さないが、このようなアリとの生活を回顧する著書ができた機会に、深く感謝していることを改めて述べたいと思う。
また、本書が成るには、野鳥社の増川百合子氏、講談社第一出版センターの井岡芳次氏、週間現代の真野純氏のご尽力に負う。ている。合わせて謝意を表したい。
師走の声を聞きながら 著者記す